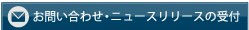丸和運輸機関、21万㎡大規模新拠点に産直PF構築

丸和運輸機関(本社・埼玉県吉川市、和佐見勝社長)は2024年度中の立上げを予定する、建設面積約20・7万㎡、総投資額400億円の大規模物流拠点「食品物流センター(仮称)=写真」(埼玉県松伏町)内に、青果物の新たな物流ターミナル「産直プラットフォーム(PF)」拠点の開設を計画する。同社ではこれまでも「AZ‐COM 7PL」で食品スーパーマーケット店舗や商品の調達を物流から支援してきたが、産直PFの構築で青果物のさらなる物流効率化と鮮度向上を実現し、食品スーパーの収益拡大に貢献する。
卸売市場法の改正で物流最適化が可能に
産直PFは、市場経由や産地直送で食品スーパーに納品される生鮮品の物流及び商流を最適化する仕組み。産地側のJA、卸売市場や集出荷業者といった広域物流集出荷拠点から発送された青果物を、消費地側の産直PF拠点で一旦集約し、同所で配送先別に仕分けた上で、食品スーパーの物流センターへ共配便などで発送するもの。まとまったロットで出荷された青果物は、食品スーパーの物流センターへの直送も可能。産直PF拠点と同一センター内に食品スーパーの物流センターを構えれば、センター間の横持ち輸送の削減とコールドチェーンの一気通貫が可能となる。
背景にあるのは、昨年6月に施行された改正卸売市場法による「商取引の自由化」だ。市場取引による青果の物流ではこれまで「商物一致」のもと、商品は市場を経由して小売店や外食店舗などへ届けられていることが大半で、青森で収穫された野菜が東京の大田市場に運ばれ、再度青森へ配送されるような物流の非効率さも生じていることもあった。
産直PFでは改正卸売市場法の「第三者への販売禁止の撤廃」により実現した産地の卸売業者からの直仕入れ品を扱うことで、より効率的な配送を実現する。さらに、産直PFに青果物の袋詰めなどの流通加工機能も持たせることで、人材確保に悩む食品スーパー側の業務もアウトソーシングでき、こうした生鮮品の流通加工作業には、丸和運輸機関が長年の食品スーパーや生協の物流で蓄積したノウハウも発揮できるという。
また、青果市場では物流動線が整流化されていなかったり、冷蔵設備のキャパシティー不足、さらにはシステム化が未整備だったりすることから、納品トラックの荷降ろしに時間が掛かり、結果として運ばれる青果物の鮮度や品質の低下につながっていたが、産直PF拠点はDX(デジタルトランスフォーメーション)化で荷降ろし作業時間を短縮。庫内も低温管理とし、輸配送と合わせたコールドチェーンを完備することで、小売店に鮮度の高い青果物を届けられる体制を作る。
こうした高度な物流機能を、自社単独で持つことが難しい、消費地の市場や地域の食品スーパーなどでシェアすることにより、“より良い商品を、より鮮度高く、より安く”店舗に並べられるようにすることが目的。鮮度の良い商品は販売数が増え、ロス率も下がるため、売上拡大のみならず利益も向上する。青果物を目当てに来店客が増えれば、店舗全体の収益拡大にも直結する。実際に、同様のシステムを先行して導入した食品スーパーでは仕入れコストが15%以上低減した商品があったうえに、「数字以上の効果が表れている」と歓迎されているという。
産直PFは、すでに関西丸和ロジスティクスの「AZ‐COMロジスティクス京都」(京都府八幡市)内にて一部稼働中にあり、埼玉県に新設する新拠点では同所の機能のさらなる高度化と大規模化を想定する。加えてファクタリング(代金決済)機能の付与や、将来的には外食産業や国産の冷凍野菜などとのシェアリングも検討していく。
幹線輸送はモーダルミックス、12ftクールコンテナも強み
青果物の物流では大産地と消費地が離れていることも、ドライバー不足や労務管理の厳格化への対応において大きな課題となっていた。そこで、産地広域物流集出荷拠点と、消費地側の産直PF拠点を結ぶ幹線便においては、トラックのみならず鉄道や海上輸送、航空輸送など複数の輸送モードを最適に使用する“モーダルミックス”を用いる。従来の青果物流通では出荷日から市場到着までのリードタイムに制限があったことから鉄道や船舶の利用が難しかったが、モーダルミックスを用いて、柔軟な活用ができるようになったという。
輸送モードの中でとくに注目するのが、グループの丸和通運が運用する12ftクールコンテナだ。同コンテナは内部の温度を定温で維持できるため、青果物ごとに最適な温度管理下で鮮度を保ったまま運ぶことが可能。主に北海道~関西以西などの長距離輸送での利用を予定するほか、大型トラックを満載にできない小ロットの輸送にも適している。鉄道を利用することでドライバー不足や労務管理対策に加え、CO2排出量削減にも寄与する。
また、航空会社と連携した国内スピード輸送にも着目。航空便を使えば、北海道で早朝収穫された生鮮品が同日夕方には関東に到着し、同日夕方~翌日早朝には売場に並べることができる。航空会社や食品スーパーなどと連携し、こうした「朝採れ野菜」のブランド化と併せて具体化を図る。海上輸送については北海道~関東を結ぶRORO船の活用を検討。スペースに余裕が生じている航路の活用を視野に入れる。
頼れるパートナーとして店舗の収益拡大に貢献
青果の物流においてはこれまでも、一企業が特定産地と直接取引する「産直」では物流ルートを最適化できた。しかし、契約産地が天候不順に見舞われると仕入れを確保できないリスクも負っていた。こうしたリスクを回避するJAや集出荷業者の “集荷・出荷”機能を維持した上で、物流を“別建てで”改革できることがポイントとなる。丸和運輸機関の谷津恭輔・営業部副部長は「青果はスーパー店舗の独自性そのもので、物流改革に最も着手すべきだったジャンル。それが可能になった意義は大きい」と、指摘する。
ただ、産直PF事業単体での収益化は考えてはおらず、同社のブランディングのひとつである、「店舗の売上が拡大すれば、丸和運輸機関が受託する物流収入が増える」との発想にある。すでに高度化された食品流通3PLにおいてオペレーションレベルに大きな差を作ることは難しいが、パートナーの立場から荷主企業である食品スーパーの収益拡大を提案できれば、他社にない付加価値を提供できる。「目指すのは、物流下請け会社的な立場ではなく、店舗運営、商品調達を含めた、経営改革の頼れるパートナー」と谷津氏は話す。
(2021年4月15日号)