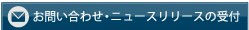申告官署自由化から3年、通関業の変化は…

2017年10月8日の輸出入申告官署の自由化、通関業法の改正から3年が経過した。全国の通関業者(法人)におけるAEO通関業者の割合はすでに2割を超え、通関営業所の集約・統合なども背景に、全国の通関営業所数は3年間で約70ヵ所減少。新型コロナウイルス感染拡大による申請要件緩和を受け、全国の通関業者の3割超が在宅勤務を申請するなど、通関業務のあり方や通関士の働き方が変わろうとしている。
柔軟な手続き体制、事業継続に寄与
17年10月8日、輸出入申告官署の自由化の実施とともに、50年ぶりに通関業法が改正され、通関業の営業区域制限が廃止。AEO通関業者は貨物の蔵置場所や通関営業所の所在に制約されない“オールフリー”の通関手続きが行えるようになった。18年9月、関西国際空港に甚大な被害をもたらした台風21号では、申告官署の自由化を活用して柔軟な通関手続き体制をとることができ、通関業者の事業継続に大きく寄与した。
AEO通関業者は自社の利便性や取り扱い貨物に合わせて柔軟に申告先を変更・集約できるようになったほか、人員配置の効率化を図るため、通関営業所の集約・統合も可能になった。全国の通関営業所数は申告官署の自由化前の17年4月時点に2131ヵ所だったのが、20年4月時点は2065ヵ所に減少。「申告官署の自由化がどの程度影響したかはわからない」(財務省関税局)が、実際にこの3年間で約70ヵ所減った。
なお、AEO通関業者の認定数については、やや落ち着きがみられる。19年のAEO通関業者の認定数は12者となり、18年の32者と比べ6割減少。申告官署の自由化に合わせて、17年に認定数が過去最高となって以降は減少基調が続いている。ただ、20年10月1日時点のAEO通関業者数は226者となり、AEO輸出者(20年10月1日)の231者を追い抜く寸前にあり、AEO事業者の中核を占めようとしている。
在宅勤務はBCP対策、OCR活用も
通関業者の働き方に大きな変化をもたらしたのが新型コロナウイルス感染症だ。財務省関税局は3月上旬から、コロナ感染対策として通関業務の在宅勤務等の開始について、税関への申請に必要な就業規則、社内管理規定を急に準備するのが難しいことから、これらの要件を緩和する弾力的な運用を実施。自宅だけでなく、サテライトオフィスについての申請も認めた。これを機に申請数は増加を続け、10月1日時点で4045人について申請が行われている。
通関業務の在宅勤務は、17年10月8日の通関業法基本通達改正によって新たに可能になったが、コロナ前はほとんど浸透していなかった。大阪通関業会(米澤隆弘理事長)の昨年のアンケートでは通関業務の在宅勤務の導入状況は、「導入している」は2%、「導入について検討中」が3%とわずかで、「現在、導入は考えていない」は67%と7割弱あったが、コロナで導入・検討を迫られることとなった。
ただ、4000人超について在宅勤務の「申請」が行われているが、どの程度が実際に「実施」されているかは不明。関係者によると「感染拡大により出勤不可能になった場合のBCP対策」に申請しておくケースが多いという。在宅勤務申請に本来必要な、就業規則や社内管理規則を整備した上での通常の申請はまだ90人程度にとどまっており、コロナ収束後、弾力的な運用が終了した際にはあらためて体制整備が必要となる。
通関業界の働き方改革にも進展がみられる。大手物流会社ではAI‐OCR技術を通関業務の帳票処理などに導入する動きがあり、手入力ミスの削減や時間短縮などのメリットが報告され、将来的な人手不足対応にも効果が期待される。税関の中長期ビジョン「スマート税関構想2020」では通関手続きの一層のデジタル化が掲げられており、通関業者もこれに合わせた業務の革新が求められそうだ。
EPA/FTA拡大、原産地規則習熟が必要に
通関業務を巡る変化としては、経済連携協定(EPA/FTA)の進展による手続きの複雑化も挙げられる。18年12月のTPP11(米国を除く11ヵ国による環太平洋経済連携協定)、19年2月の日EU・EPAと大型EPAが発効し、20年8月時点で日本は21ヵ国・地域と19のEPA/FTA等が発効済・署名済。発効済・署名済の相手国との貿易が貿易総額に占める割合は52・4%、交渉中の者も含めると86・1%となる。
EPA/FTAの拡大に伴い通関手続きにおいてはEPA原産地規則の習熟が求められるようになり、日本通関業連合会(岡藤正策会長)でも専門研修の充実を図っている。TPP11や日EU・EPAなどで導入されている「自己申告制度」では、「原産品申告書」を通関業者が代理作成する新たな業務が期待されていたが、荷主への説明の負担や、業務の対価の面で課題があり、積極的には進んでいないようだ。
(2020年10月8日号)