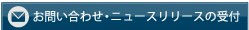物流不動産、共通トレンドと差別化戦略は?

コロナ禍でのEC需要の高まりを受け、物流不動産の開発がますます活発化している。足元の需要は堅調で、首都圏では過去最低の空室率を維持。入居企業のコスト意識が厳しいとされてきた近畿圏でも賃料上昇がみられる。実需の支えと金融緩和を背景とした投資家マネーの投入が掛け合わされて大量供給が続く物流不動産市場。その共通トレンド、各プレイヤーの差別化戦略に迫る。
ラストワンマイル、自動化ニーズに対応
共通トレンドのひとつが「都市型」傾向だ。ECの伸長は消費者へのラストワンマイル圏での物流施設需要急増につながっており、都市型配送に最適な拠点を開発する動きがみられる。先行するのがプロロジス。「プロロジスアーバン」という新ブランドを掲げ、東京都内ですでに2物件を開設、1物件も来年2月に竣工予定だ。このほど7件の新規開発を発表した三井不動産も「アーバン型MFLP」の展開を打ち出す。
物流業界の労働力不足を背景とした省人化・省力化、コロナ禍での“非接触”ニーズに対応するため、テック企業との連携もトレンドとして定着した。典型とされるのが、大和ハウス工業が千葉県市川市で開設した、AI、IoT、ロボティクスを活用し、物流効率化、省人化を実現するためのプラットフォームを取り入れた施設「Intelligent Logistics Center PROTO」だ。
他のプレイヤーもテック企業との連携を強化する。野村不動産は、自動化機器の効率的な活用により物流オペレーションの最適化を実現する企業間共創プログラム「Techrum(テクラム)」を4月より開始し、効果検証拠点である「習志野 PoC Hub」を開設。三井不動産も、「MFLP ICT LABO 2.0」を活用した先進的オートメーション倉庫の実現に向けた検討を進めていくとしている。
冷凍冷蔵倉庫に注力、太陽光は「自家消費型」に
伸びしろが大きいとされる食品のEC需要をにらみ、冷凍冷蔵倉庫への投資もみられる。マーケットでは後発の霞ヶ関キャピタルは、7件の物流施設計画のうち4件が冷凍冷蔵倉庫と注力が目立つ。従来、冷凍冷蔵倉庫は金融商品としての流動性が低いため不動産投資の対象にそぐわない面もあったが、老朽化に伴う建て替えの潜在需要が見込まれ、大和ハウス工業、三井不動産も冷凍冷蔵倉庫への開発意向を示す。
世界的なESG投資の流れを受けて、物流不動産も一層、その対応が色濃くなる。環境対策の一環として物流施設の屋上に太陽光発電システムを搭載する傾向は変わらないが、ESRなどでは「売電型」から施設内での「自家消費型」にシフトがみられる。また、東京建物は東京ガスと連携し、埼玉県久喜市の物流施設の自家消費型太陽光発電システムで余った発電量を他の施設に自己託送する新たな仕組みを導入する。
地方開発、「カテゴリーマルチ」などで特色
差別化戦略についてはどうか。大和ハウス工業は、大都市圏のみならず、地方での開発に意欲をみせる。オープンハブ、インテグレーテッドチェーン、シェアードソリューションをコンセプトとした日本GLPの大規模面開発「GLP ALFALINKシリーズ」、汎用スペックに業種ごとのカテゴリー特有の機能を標準仕様として付加した野村不動産の「カテゴリーマルチ」といった施設設計も特色がある。
CBREの調査レポートによると、2021年には首都圏では約211万㎡の供給が見込まれ、「立地やスペックによる競争力の差が表面化する可能性がある」とし、リーシングへの影響も示唆する。SDGsの流れを受けた自治体との災害協定の締結、大規模倉庫における危険物倉庫の併設、データセンター用途の検討など社会的なニーズを見据えた新たなトレンドも予想される。
(2021年4月8日号)